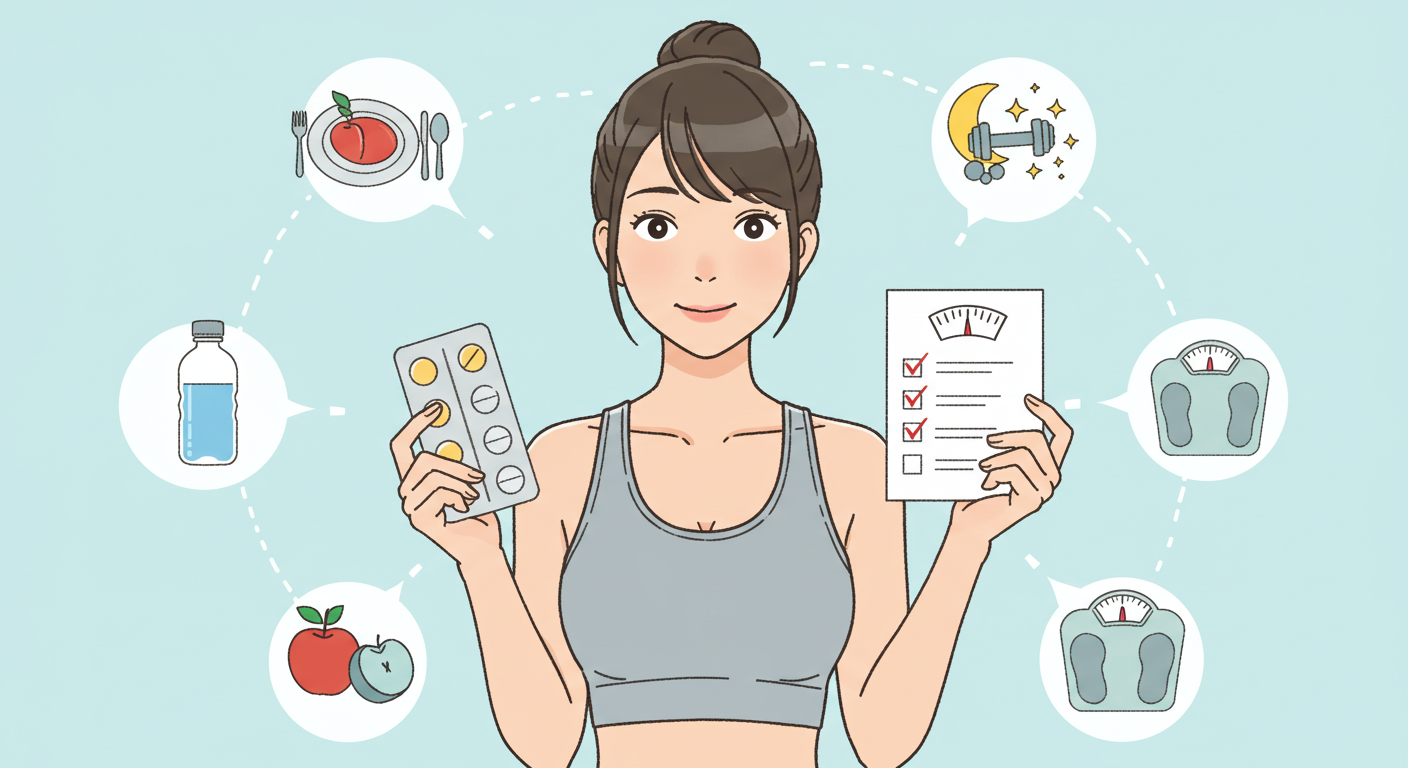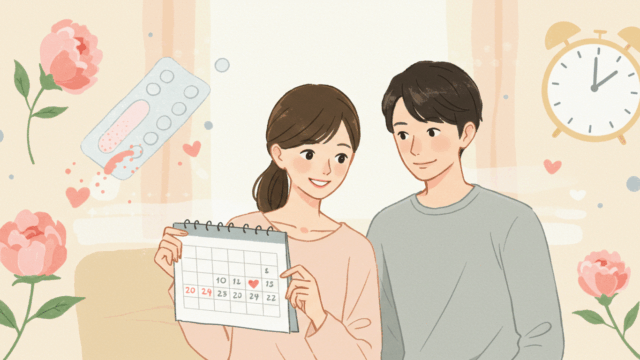ピル代を安く抑える5つの方法|費用負担を軽減する賢い選択肢
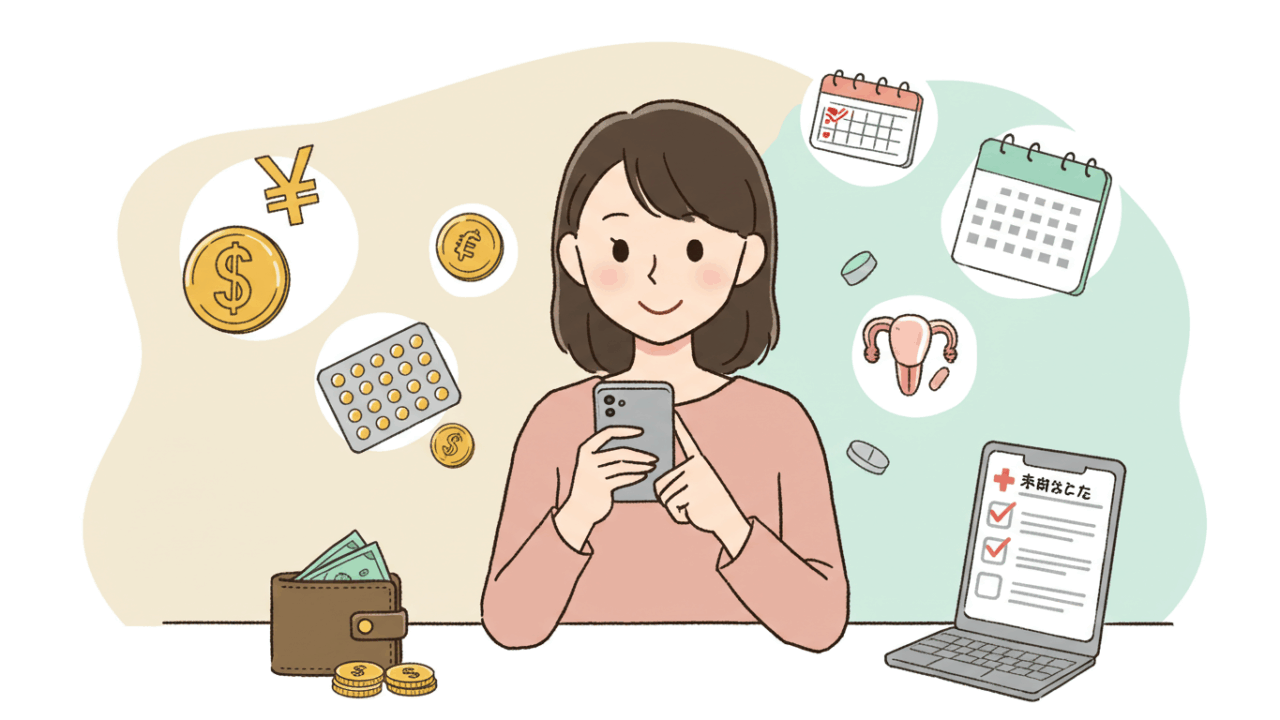
低用量ピルは女性の健康管理や人生設計において重要な選択肢の一つですが、継続的な服用には相応の費用がかかります。自費診療が基本となることが多いため、月々の出費が家計の負担となっている方も少なくありません。
「ピルを続けたいけれど、費用が心配」「もう少し安く済ませる方法はないの?」そんな悩みをお持ちの方のために、この記事では低用量ピルの費用を抑える具体的な方法をご紹介します。
ただし、費用の削減を考える際も、安全性と有効性を最優先に考えることが重要です。適切な医師の指導のもとで、経済的負担と医療の質のバランスを取りながら、最適な選択肢を見つけていきましょう。
低用量ピルの費用相場と現状
一般的な費用の内訳
低用量ピルの費用を理解するために、まずは一般的な費用構造を把握しておきましょう。ピル処方にかかる費用は、主に以下の要素で構成されています。
初診時の費用
- 初診料:2,000〜5,000円程度
- 診察・カウンセリング料:1,000〜3,000円程度
- 検査費用:3,000〜10,000円程度(血液検査、血圧測定など)
- 薬剤費:2,000〜3,500円程度(1ヶ月分)
初回総費用として、8,000〜21,500円程度が相場となっています。医療機関や検査内容によって大きく異なりますが、この初期費用が最も大きな負担となることが多いです。
継続時の費用
- 再診料:1,000〜2,000円程度
- 薬剤費:2,000〜3,500円程度(1ヶ月分)
- 定期検査費用:3,000〜8,000円程度(3〜6ヶ月ごと)
継続時は月額3,000〜5,500円程度が一般的で、年間では36,000〜66,000円程度の費用がかかることになります。
地域差と医療機関による違い
ピルの費用は地域や医療機関によって大きく異なります。都市部では競合が多いため比較的安価な場合もある一方、専門クリニックでは高額になることもあります。
また、大学病院などの大規模医療機関では初診料が高めに設定されていることが多く、個人クリニックでは比較的リーズナブルな場合もあります。事前に複数の医療機関で費用を確認することが重要です。
方法1:保険適用条件を活用する
保険適用が可能なケース
低用量ピルは基本的に自費診療となりますが、特定の条件下では保険適用となる場合があります。これを理解して活用することで、大幅な費用削減が可能です。
月経困難症の治療目的
月経困難症(生理痛が日常生活に支障をきたすレベル)の治療目的でピルが処方される場合、保険適用となることがあります。この場合、3割負担で済むため、月額の費用を大幅に抑えることができます。
月経困難症による保険適用の条件:
- 月経時の強い痛みが毎回ある
- 鎮痛薬を使用しても痛みが十分に軽減されない
- 日常生活や仕事に支障をきたしている
- 医師が月経困難症と診断している
子宮内膜症の治療
子宮内膜症の診断を受けている場合、その治療の一環として低用量ピルが処方されることがあり、この場合も保険適用となります。子宮内膜症は進行性の疾患であるため、早期の診断と治療が重要です。
機能性月経過多の治療
月経量が異常に多く、日常生活に支障をきたしている場合、機能性月経過多の治療として低用量ピルが保険適用で処方されることがあります。
保険適用を受けるための手順
適切な診察を受ける
保険適用を受けるためには、まず医師による適切な診察と診断が必要です。症状について詳しく説明し、必要に応じて検査を受けることで、治療目的であることを明確にします。
診察時に伝えるべき症状:
- 月経痛の程度と持続時間
- 鎮痛薬の使用頻度と効果
- 日常生活への影響度
- 月経量や月経周期の異常
- その他の随伴症状
治療用ピルの処方
保険適用の場合、避妊目的のピルとは異なる「治療用ピル」が処方されます。これらは同じ成分を含んでいても、適応症や製品名が異なる場合があります。
代表的な保険適用ピル:
- ルナベル配合錠(LD/ULD)
- フリウェル配合錠(LD/ULD)
- ヤーズ配合錠
- ヤーズフレックス配合錠
保険適用時の費用比較
保険適用となった場合の費用削減効果は非常に大きく、自費診療の場合と比較して月額費用を2,000〜3,000円程度削減できる可能性があります。
| 項目 | 自費診療 | 保険適用 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 薬剤費(月額) | 2,500〜3,500円 | 800〜1,200円 | ▲1,700〜2,300円 |
| 再診料 | 1,500〜2,500円 | 500〜800円 | ▲1,000〜1,700円 |
| 年間総費用 | 48,000〜72,000円 | 15,600〜24,000円 | ▲32,400〜48,000円 |
方法2:ジェネリック医薬品を選択する
ジェネリック医薬品の基礎知識
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同じ有効成分を含み、同等の効果が期待できる医薬品です。開発コストが抑えられているため、先発品よりも安価で提供されています。
ジェネリック医薬品の特徴
- 有効成分:先発品と同一
- 効果・安全性:先発品と同等であることが確認済み
- 価格:先発品の50〜80%程度
- 外観:錠剤の色や形状が異なる場合がある
- 添加物:一部異なる場合があるが、安全性は確認済み
低用量ピルのジェネリック医薬品
現在、日本で利用可能な低用量ピルのジェネリック医薬品には以下のようなものがあります。
主要なジェネリック医薬品
- フリウェル配合錠:ルナベル配合錠のジェネリック
- ドロエチ配合錠:ヤーズ配合錠のジェネリック
- レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠:各種先発品のジェネリック
費用削減効果
ジェネリック医薬品を選択することで、薬剤費を20〜50%程度削減できる場合があります。
| 先発品 | ジェネリック品 | 価格差(月額) |
|---|---|---|
| ルナベルLD | フリウェルLD | 約500〜800円削減 |
| ヤーズ | ドロエチ | 約600〜1,000円削減 |
ジェネリック医薬品選択時の注意点
医師との相談
ジェネリック医薬品への変更は、必ず医師と相談して決定しましょう。個人の体質や症状によっては、先発品の方が適している場合もあります。
効果の確認
ジェネリック医薬品に変更した後は、効果や副作用に変化がないか注意深く観察し、定期的に医師に報告することが重要です。
薬局での確認
処方箋を受け取る際に、薬剤師にジェネリック医薬品の希望を伝えることができます。ただし、医師が特に先発品を指定している場合は、その理由を確認することが大切です。
方法3:オンライン診療を活用する
オンライン診療の仕組み
オンライン診療は、スマートフォンやパソコンを使用してビデオ通話で医師の診察を受けることができるサービスです。2020年以降、その利用が拡大し、ピル処方においても選択肢の一つとなっています。
オンライン診療の流れ
- アプリ登録・予約:専用アプリやウェブサイトから登録・予約
- 問診票記入:事前に詳細な問診票を記入
- ビデオ診察:医師とのビデオ通話による診察
- 処方・決済:処方箋の発行と診療費の決済
- 薬の受取:指定薬局での受取または配送
オンライン診療のメリット
通院時間・交通費の削減
オンライン診療を利用することで、医療機関への移動時間や交通費を削減できます。特に遠方の専門クリニックを利用している場合、この効果は大きくなります。
診療費の抑制
オンライン診療専門のクリニックでは、設備費などのコストを抑えられるため、対面診療よりも安価な料金設定となっている場合があります。
時間の有効活用
待ち時間がなく、予約時間通りに診察が受けられるため、時間を有効活用できます。これにより、仕事を休む必要もなく、間接的な経済効果も期待できます。
オンライン診療の費用例
オンライン診療での低用量ピル処方の費用例をご紹介します。
| 項目 | オンライン診療 | 対面診療 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 初診料 | 1,500〜3,000円 | 2,500〜5,000円 | ▲1,000〜2,000円 |
| 再診料 | 1,000〜1,500円 | 1,500〜2,500円 | ▲500〜1,000円 |
| 薬剤費 | 2,200〜3,000円 | 2,500〜3,500円 | ▲300〜500円 |
| 配送料 | 300〜500円 | 交通費500〜2,000円 | ▲200〜1,500円 |
オンライン診療の注意点
適用条件
オンライン診療でピル処方を受けるには、一定の条件があります:
- 過去に同じ医療機関で対面診療を受けた経験がある(初診からオンラインのみのサービスもある)
- 安定した症状で継続処方が適切と判断される
- 定期的な検査が必要でない状態
- 緊急時に対面診療を受けられる体制がある
技術的要件
安定したインターネット環境と、ビデオ通話が可能なデバイスが必要です。また、診察時間中は静かで プライバシーが保たれる環境を確保することが重要です。
薬の受取方法
処方された薬は、指定薬局での受取または配送で入手します。配送の場合、薬事法の関係で薬剤師による服薬指導が必要となる場合があります。
方法4:医療機関の比較検討
費用比較の重要性
ピルの処方費用は医療機関によって大きく異なります。同じ薬を処方されても、月額で1,000〜2,000円の差が生じることも珍しくありません。継続的に服用することを考えると、この差は年間で12,000〜24,000円にもなります。
比較すべき医療機関の種類
婦人科専門クリニック
特徴:
- ピル処方に特化した豊富な経験
- 多様なピルの選択肢
- 女性特有の症状への理解が深い
- プライバシーへの配慮
費用傾向:中程度〜やや高め(月額3,000〜5,000円程度)
総合病院・大学病院
特徴:
- 総合的な健康管理が可能
- 他科との連携が取りやすい
- 重篤な副作用への対応力
- 研修医による診察の場合がある
費用傾向:やや高め(初診料が高く設定されていることが多い)
内科・家庭医
特徴:
- 総合的な健康管理
- 長期的な関係構築
- 他の健康問題との総合的な管理
- ピル処方の経験に差がある場合も
費用傾向:比較的安価(月額2,500〜4,000円程度)
ピル専門オンラインクリニック
特徴:
- ピル処方に特化
- オンライン完結型サービス
- 定期配送サービス
- 24時間対応の場合も
費用傾向:比較的安価(月額2,200〜3,500円程度)
費用比較時のチェックポイント
基本料金の内訳
各医療機関で以下の項目を確認しましょう:
- 初診料:初回診察にかかる費用
- 再診料:継続診察にかかる費用
- 薬剤費:ピル1ヶ月分の費用
- 検査費用:血液検査等の費用(頻度含む)
- その他費用:処方箋料、指導料等
隠れたコスト
表示されている基本料金以外にも、以下のような費用が発生する場合があります:
- 予約料やシステム利用料
- カウンセリング料
- 時間外診療料
- 処方箋の郵送料
- 薬の配送料
継続利用時の割引制度
長期継続利用者向けの割引制度がある医療機関もあります:
- まとめ処方割引(3ヶ月分、6ヶ月分等)
- 継続利用割引
- 学生割引
- 家族割引
医療機関選択時の注意点
安全性の確保
費用だけでなく、以下の安全性も重視しましょう:
- 医師の資格と経験
- 適切な診察・検査体制
- 緊急時の対応体制
- 薬剤の品質管理
アクセシビリティ
継続的な通院を考慮したアクセシビリティも重要です:
- 立地・交通の便
- 診療時間
- 予約の取りやすさ
- 待ち時間
方法5:まとめ処方・定期配送サービスを利用する
まとめ処方のメリット
一度に複数ヶ月分のピルを処方してもらうことで、受診回数を減らし、全体的な費用を抑えることができます。また、薬切れのリスクも軽減できるため、継続的な服用に適した方法です。
費用削減効果
まとめ処方により削減できる費用の例:
| 処方期間 | 受診回数(年間) | 再診料(年間) | 節約効果 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月ごと | 12回 | 18,000円 | 基準 |
| 3ヶ月ごと | 4回 | 6,000円 | ▲12,000円 |
| 6ヶ月ごと | 2回 | 3,000円 | ▲15,000円 |
まとめ処方の条件
医学的条件
まとめ処方を受けるためには以下の条件を満たす必要があります:
- 服用開始から一定期間が経過している(通常3〜6ヶ月)
- 副作用や異常な症状がない
- 血圧や体重が安定している
- 定期検査の結果に問題がない
- 服薬コンプライアンスが良好
法的制限
日本では、医師法により一度に処方できる薬の量に制限があります。低用量ピルの場合、一般的には最大90日分(約3ヶ月分)までとされています。
定期配送サービス
オンライン診療と組み合わせた定期配送サービスを利用することで、さらなる利便性と費用削減が可能です。
定期配送のメリット
- 継続割引:定期契約による料金優遇
- 配送料優遇:まとめ配送による送料削減
- 飲み忘れ防止:自動配送による継続サポート
- 時間節約:受診・薬局来店の時間削減
主要なサービス例
現在利用可能な主要な定期配送サービス:
- 月額定額制:月々一定額での定期配送
- まとめ支払い制:3ヶ月、6ヶ月分の前払い割引
- ポイント制:継続利用によるポイント還元
- 紹介割引:友人紹介による割引制度
まとめ処方・定期配送利用時の注意点
品質管理
長期保存や配送による薬剤の品質への影響を考慮する必要があります:
- 適切な保存環境の確保(温度・湿度管理)
- 有効期限の確認
- 配送時の温度管理
- 梱包の適切性
健康状態の変化への対応
まとめ処方期間中に健康状態が変化した場合の対応策を確認しておきましょう:
- 緊急連絡先の確保
- 定期的な自己チェック方法
- 異常時の服用中止基準
- 臨時受診の手順
費用削減時の安全性確保
安全性を損なわない費用削減の原則
ピル代を抑えることは重要ですが、安全性を犠牲にしてはいけません。以下の原則を守りながら費用削減を行いましょう。
適切な医療機関の選択
費用が安いからといって、以下のような医療機関は避けるべきです:
- 医師の資格が不明確
- 適切な診察を行わない
- 検査を全く実施しない
- 緊急時の対応体制が不明
- 薬剤の出所が不明
必要な検査の省略は避ける
費用を抑えるために以下の必要な検査を省略するのは危険です:
- 血圧測定
- 血液検査(初回・定期)
- 体重・BMI測定
- 問診・症状確認
- 乳房・腹部の診察
正規品の確保
個人輸入の危険性
費用を抑えるために海外からの個人輸入を検討する方もいますが、以下のリスクがあります:
- 品質の保証がない:偽造品や不良品のリスク
- 副作用対応の困難:医師の管理下にない服用
- 法的問題:薬事法違反の可能性
- 緊急時対応:適切な医療機関での対応が困難
- 配送リスク:税関での没収可能性
正規品確認のポイント
正規品を確実に入手するために:
- 医療機関での正規処方を受ける
- 薬局で薬剤師による説明を受ける
- パッケージの製造販売業者を確認
- ロット番号や有効期限の確認
学生・若年層向けの費用軽減策
学生向け割引制度
一部の医療機関では、学生向けの特別料金を設定している場合があります。
利用可能な割引例
- 学生証提示割引:10〜20%の料金減額
- 初診料無料:学生の初回診察料免除
- 検査費用軽減:必要最小限の検査による費用抑制
- 相談料免除:服薬指導やカウンセリング料の免除
学生支援制度のある医療機関
以下のような医療機関で学生向けサービスを提供している場合があります:
- 大学病院・附属病院
- 学生健康管理センター
- 若年女性支援クリニック
- 婦人科専門クリニック
家族計画指導との連携
自治体や保健所で実施されている家族計画指導と連携することで、費用軽減につながる場合があります。
自治体サービスの活用
- 相談窓口:無料の避妊相談サービス
- 健康診断:女性の健康診断での総合評価
- 教育プログラム:正しい知識習得による適切な選択
- 医療機関紹介:適切な医療機関の紹介サービス
長期的な費用計画
年間・長期コストの計算
ピル代の費用を考える際は、短期的な月額費用だけでなく、年間や長期的なコストを計算することが重要です。
総費用計算の要素
年間の総費用には以下の要素が含まれます:
- 薬剤費:月額×12ヶ月
- 診察費:受診回数×再診料
- 検査費:定期検査費用
- 交通費:通院にかかる交通費
- 時間コスト:通院時間の機会費用
5年間の費用比較例
| 選択肢 | 年間費用 | 5年間総額 | 節約効果 |
|---|---|---|---|
| 一般クリニック(自費) | 60,000円 | 300,000円 | 基準 |
| 保険適用 | 20,000円 | 100,000円 | ▲200,000円 |
| オンライン+ジェネリック | 35,000円 | 175,000円 | ▲125,000円 |
| まとめ処方活用 | 45,000円 | 225,000円 | ▲75,000円 |
ライフステージ別費用計画
学生期(18〜22歳)
収入が限られる学生期には、以下の戦略が有効です:
- 学生割引制度の積極的活用
- 保険適用条件の確認
- 家族の健康保険の活用
- 自治体サービスの利用
社会人初期(23〜28歳)
安定した収入が得られる一方で、初期費用を抑えたい時期:
- 職場近くの利便性重視
- オンライン診療の活用
- まとめ処方による効率化
- ジェネリック医薬品の選択
キャリア期(29〜35歳)
収入は安定するが、時間的制約が大きい時期:
- 時間効率を重視した選択
- 定期配送サービスの活用
- 質の高い医療機関の選択
- 長期的な健康投資の観点
費用に関するよくある質問
制度・保険に関する質問
Q: 医療費控除の対象になりますか?
A: 避妊目的のピル代は医療費控除の対象外ですが、月経困難症などの治療目的で保険適用となった場合は対象となります。領収書を保管し、税務署または税理士にご相談ください。
Q: 健康保険組合の付加給付は利用できますか?
A: 保険適用のピル処方については、加入している健康保険組合によっては付加給付の対象となる場合があります。詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
Q: 生活保護受給中でもピルは処方してもらえますか?
A: 治療目的で医師が必要と判断した場合、医療券による保険適用での処方が可能です。福祉事務所のケースワーカーにご相談ください。
医療機関選択に関する質問
Q: 安い医療機関と高い医療機関の違いは何ですか?
A: 費用の違いは、立地、設備、サービス内容、検査の充実度などによります。重要なのは費用と安全性・サービスのバランスです。極端に安い場合は、必要な検査が省略されていないか確認しましょう。
Q: 医療機関を変更する際の注意点は?
A: 紹介状や過去の検査結果を新しい医療機関に提供することで、重複検査を避けられます。また、服用中のピルの種類や服用歴を正確に伝えることが重要です。
ジェネリック医薬品に関する質問
Q: ジェネリック医薬品に変更して効果が変わることはありますか?
A: 基本的に先発品と同等の効果が期待できますが、添加物の違いにより個人差が生じる場合があります。変更後は体調の変化を注意深く観察し、問題があれば医師に相談してください。
Q: ジェネリック医薬品は自分で選択できますか?
A: 医師がジェネリック医薬品への変更を不可としていない場合、薬局で薬剤師と相談して選択できます。ただし、医学的理由で先発品が指定されている場合は、その理由を確認することが大切です。
今後の制度変更と展望
ピル処方に関する制度の動向
低用量ピルを取り巻く制度や環境は徐々に変化しており、将来的にはより利用しやすくなる可能性があります。
オンライン診療の拡充
2020年以降、オンライン診療の規制緩和が進んでおり、今後はより多くの医療機関でオンライン診療によるピル処方が可能になると予想されます。これにより、選択肢の増加と費用の競争による価格低下が期待できます。
薬局での取り扱い拡大
将来的には、諸外国のように薬局での直接購入(OTC化)が検討される可能性もあります。これが実現すれば、診察費用が不要となり、大幅な費用削減につながる可能性があります。
新しいサービスの登場
サブスクリプション型サービス
月額定額制でピルの処方から配送までを一括で提供するサブスクリプション型サービスが増加しています。これらのサービスは利便性と費用効率を両立させる新しい選択肢となっています。
AIを活用した個別化サービス
人工知能を活用して個人の症状や体質に最適なピルを提案するサービスの開発が進んでいます。これにより、より効果的で副作用の少ない治療が可能になり、結果的に長期的な費用削減につながる可能性があります。
実践的な費用削減プラン
段階別実施プラン
ピル代の費用削減は、一度に大きく変更するのではなく、段階的に実施することをお勧めします。
第1段階:情報収集(1ヶ月目)
- 現在の費用の詳細把握
- 近隣医療機関の費用調査
- 保険適用条件の確認
- オンライン診療サービスの調査
第2段階:比較検討(2ヶ月目)
- 複数の医療機関での見積り取得
- ジェネリック医薬品の確認
- まとめ処方の可能性確認
- 年間費用の詳細計算
第3段階:実施・移行(3ヶ月目)
- 最適な医療機関への変更
- ジェネリック医薬品への変更
- まとめ処方の開始
- 定期配送サービスの利用開始
第4段階:効果検証(4〜6ヶ月目)
- 費用削減効果の測定
- サービス満足度の評価
- 健康状態への影響確認
- 必要に応じた調整・改善
費用削減チェックリスト
効果的な費用削減のために、以下のチェックリストを活用してください。
基本事項確認
- □ 現在の月額費用を正確に把握している
- □ 年間総費用を計算している
- □ 保険適用の可能性を確認した
- □ 複数の医療機関を比較した
- □ ジェネリック医薬品について確認した
安全性確認
- □ 選択した医療機関の信頼性を確認した
- □ 必要な検査が適切に実施される
- □ 緊急時の連絡体制が確保されている
- □ 薬剤の品質管理体制を確認した
- □ 定期的な健康チェックが継続できる
利便性確認
- □ 通院・受診の利便性が確保されている
- □ 薬の受取方法が確立されている
- □ 長期的な継続が可能である
- □ ライフスタイルに適合している
- □ 満足度が向上している
まとめ
低用量ピルの費用を抑える方法は多岐にわたり、適切な選択により年間数万円の節約が可能です。この記事でご紹介した5つの主要な方法を振り返ってみましょう。
方法1:保険適用条件の活用では、月経困難症や子宮内膜症などの治療目的でピルが処方される場合、保険適用により大幅な費用削減が可能であることをご説明しました。年間で30,000〜50,000円程度の節約効果が期待できます。
方法2:ジェネリック医薬品の選択では、先発品と同等の効果を持ちながら、20〜50%程度安価なジェネリック医薬品を選択することで、月額500〜1,000円程度の節約が可能であることをご紹介しました。
方法3:オンライン診療の活用では、通院時間や交通費の削減に加え、診療費自体も抑えられる可能性があることをお伝えしました。特に忙しい方や遠方にお住まいの方には大きなメリットがあります。
方法4:医療機関の比較検討では、同じピルでも医療機関により月額1,000〜2,000円の差が生じることがあり、年間では12,000〜24,000円の差になることをご説明しました。
方法5:まとめ処方・定期配送サービスでは、一度に複数ヶ月分を処方してもらうことで受診回数を減らし、年間10,000〜15,000円程度の節約が可能であることをご紹介しました。
これらの方法を組み合わせることで、最大で年間50,000円以上の費用削減も可能です。ただし、費用の削減を図る際も、以下の点を必ず守ることが重要です。
- 安全性の確保:適切な医師の診察と管理下での服用
- 品質の保証:正規品の使用と適切な保管
- 継続性の確保:長期的に続けられる方法の選択
- 健康状態の監視:定期的な検査と健康チェック
また、費用削減を考える際は、短期的な月額費用だけでなく、年間や長期的な総費用を計算することが重要です。初期費用が高くても、長期的には経済的になる選択肢もあります。
ピルは女性の健康管理や人生設計において重要な選択肢です。経済的な負担を理由に継続を断念することがないよう、この記事でご紹介した方法を参考に、自分に最適な費用削減策を見つけていただければと思います。
最後に、どの方法を選択する場合も、必ず医師との相談を行い、安全性を最優先に考えることが大切です。費用と安全性、利便性のバランスを取りながら、長期的に安心して続けられる方法を選択してください。
重要なお知らせ
この記事の情報は一般的な参考情報として提供されており、個別の医学的アドバイスではありません。ピルの処方や費用に関する具体的な相談は、必ず医療機関で医師にご相談ください。
また、費用削減を目的として以下の行為は絶対に避けてください:
- 医師の処方箋なしでの薬剤入手
- 海外からの個人輸入
- 他人との薬剤の共有
- 必要な検査の省略
- 医師の指示に従わない服用
医療情報に関する注意事項
この記事に記載された情報は、一般的な情報提供を目的としており、特定の個人に対する医学的アドバイス、診断、治療の代替となるものではありません。低用量ピルの処方や費用に関する事項については、必ず医療機関を受診し、医師の診断と指導を受けてください。
費用削減を目的とした医療機関の変更やサービス利用についても、事前に医師にご相談ください。また、本記事で紹介した費用や制度は変更される可能性があります。最新の情報については、各医療機関や関係機関に直接お問い合わせください。
薬事法により、医薬品の個人輸入や無許可販売は禁止されています。必ず正規の医療機関で処方された薬剤を使用してください。